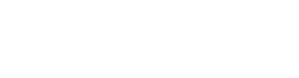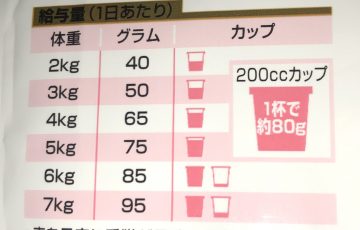ペット栄養管理士・ペットフード販売士の目から見て、信頼できるペットフードメーカーは、
「ペットフードの研究をめちゃくちゃしているメーカー」です。
終わり。

©Shutterstock
……さすがに言葉足らずなので、もう少し詳しく説明しますね。
ペットフードで重要なのは「科学」です。
フードに含まれる栄養素は、少なすぎても多すぎても健康を損ないます。
猫の場合、たんぱく質や脂質などが多いフードを好む傾向にありますが、それらが多すぎると栄養バランスが崩れます。
猫や犬が若ければすぐに問題は出にくいですが、長期的に与えたり、高齢だったりすると体調が悪くなります。
つまり栄養素の過不足がなく、一定以上の嗜好性を備え、長期的に健康を維持できるフードが望ましいわけです。
それはどうやって追い求めるのでしょうか?
ずばり「大規模かつ長期的な研究」です。
これまでの研究成果をもとに、フードの栄養設計を行う。
そのフードを猫や犬に与え、食いつきや健康状態を観察する。
結果をもとに、フードを改善する。
これがペットフード開発の基本ですが、大事なのは「規模」と「期間」です。
人間同様、猫や犬にも個体差があります。
「猫1匹・1週間の研究データをもとに開発したキャットフードです!」
うわー、不安。全然説得力がないですよね。
「猫500匹・10年間の研究データをもとに開発したキャットフードです!」
どうでしょう?
うわー、すごい。信頼できそう……と思うのではないでしょうか。
栄養学の世界では、研究の対象数と期間が一定以上なければ、科学的根拠とは認められません。
キャットフードの広告で
「猫にとって理想的な栄養バランス」
といった文言をよく目にしますが、その根拠はどこから来ているのか、
かる〜く調べてみましょう。
ペットの栄養学やペットフードの研究に力を入れているペットフードメーカーは、
必ず独自の研究施設を持ち、それをホームページなどで公開しています。
もちろん研究施設があるからといって、そのメーカーのペットフードが良質と結論づけることはできません。
でも、研究施設を持たなければ、科学的根拠のあるペットフードを作ることは極めて難しい……というかムリでしょう。
だから筆者は「ペットフードの研究をめちゃくちゃしている」メーカーが信頼できると思っているわけです。
文/奥田直樹(ペット栄養管理士/ペットフード販売士)